自分が働いている職場が活き活きとできる場であって欲しいと思うのは、立場に関わらず共通のものだと思います。活き活きとすることで、モチベーションが高まって仕事に対するやる気や工夫が増加したり、チームメンバーとのコミュニケーションや関係が向上して、協力体制が強化されたりします。その結果として、チームの成績、生産性、ひいては企業の業績が向上することが期待できます。
この記事では、前編に続いて、組織の制度や構造といったハード面だけでなく、人と人の関係などのソフト面にも着目して改革をしようという組織開発という考え方を説いた「入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる」(中村和彦著 光文社新書)について書いていきます。
前編では、なぜ組織開発が求められているのかという背景に始まり、組織開発とはなにか、その具体的な価値観や実施手法はどういったものか、と言ったことを取り上げてきました。この後は組織開発の進め方と組織開発を使って日本企業を活性化させていく道について内容を紹介していきます。
組織開発の進め方
組織開発の進め方は大別すると、①」リーダー養成型組織開発、②パートナー型組織開発、があります。前者の例としてはGE(General Electric)が有名ですが、様々な組織開発の手法は後者を前提として開発・発展してきています。以下はパートナー型組織開発について紹介します。
パートナー型組織開発では、対象となる職場の外にいる組織開発実践者(コンサルタント、または社内の実践者)が変革のパートナーとなって、職場の当事者とともに変革に取り組みます。
データフィードバックによる取り組み
この取組は文字通り、組織の現状についてのデータ収集をし、現状把握をした上で、変革アクションを決めていくやり方です。具体的なフェーズは以下のようになっていて、本書では1から4を詳説しています。
- エントリーと契約
- データ収集
- データ分析
- フィードバック
- アクション計画
- アクション実施
- 評価
- 終結
エントリーと契約
エントリーとは組織開発実践者が、対象の職場にはじめて入っていくことを指します。そして責任者と面談して、どの様な現状から、どの様な状態にすることを目指すのか、そのための取り組み方や、関係者の役割・責任といったことを話し合って合意します。これを契約と呼んでおり、心理的に組織開発にコミットすることを重要視しています。
データ収集と分析
対象となっている組織の中でどの様なプロセスが起こっているかに気づくのが目的で実施されます。対象は個人、グループ、部門間、組織全体など様々ですが、その対象などによっていくつかの手法が用いいられます。
360度フィードバック、インタビュー調査、会議や職場の観察、アンケートなどを用いて行われます。
集まったデータをもとに、組織開発実践者を中心に、フィードバックミーティングに向けた集計、分類、分析などを行います。
フィードバック
ミーティングは対象職場の全員に対して行われます。ひとつのイメージは組織開発実践者からデータ分析結果のフィードバックがされた上で、参加者たちがその内容についての気づきなどについて話をするワークショップだと理解してください。
このセッションは、データを元に職場でどんなことが起こっているのか、どんな問題があるかに気づくのが目的です。フィードバックで何らかの問題点が報告されると、すぐに解決策を持ち出す人がいますが、むしろ現在起こっていることや、それに対して各自がどの様に感じているかを共有して、変えていきたい問題点を明確にすることを目指す場の位置付けです。
プロセス・コンサルテーションによる取り組み
データフィードバックとは別の、パートナー型組織開発の取り組みとして、プロセス・コンサルテーションがあります。
コンサルタントと当事者(クライアント)の関係については以下の3つのモードがあると言われています。
- 専門家モデル (当事者は問題に気づいているが、解決策を知らない場合 → コンサルタントが情報提供や実行を担う関係性)
- 医師・患者モデル (当事者は現実に気づいていない場合 → コンサルタントがデータを集め、診断して、処方箋を出すという関係性)
- プロセス・コンサルテーションモデル (当事者がプロセスに気づき、理解し、それに従った行動ができるようになることを目指して、コンサルタントが支援する関係性)
最後に挙げた様なプロセス・コンサルテーションモデルを中心に据えて、当事者が現在の問題に自分で気づき、自分で解決策を考えて実行していく様に、コンサルタントが支援する進め方です。
その他の取り組み
本書ではその他に具体的な進め方として「対立解決セッション」や「アプリシエイティブ・インクワイアリー」といった手法が紹介されていますが、ここでは割愛します。
組織開発を有効に実践して、成果を出すための鍵
この様な様々な取り組みを通じて組織の活性化を図り、パフォーマンス向上に結びつけるのが組織開発の目的ですが、実際に効果を出していくための鍵をいくつか挙げています。
ひとつは組織開発の実践者(社内コンサルタント)をどの部署に設置するのかです。トップのもとで独立した組織、人事の配下、経営企画の中、というのが主だった考え方で、それぞれにメリット・デメリットがある訳ですが、企業によっては理念やビジョンの浸透を行う部門が担当、風土改革部門が実施などの実例もあり、それぞれの企業が自社の実情に合わせて決めていくことになります。
また組織開発は組織体質改善であり、長期間の取り組みを要することから、経営者自身が意識を変えて、組織開発が業績にも影響を与える重要事項であるという信念を持って、リーダーシップを発揮することが求められるということです。
まとめ
この記事では「入門 組織開発」 活き活きと働ける職場をつくる」の後半の、組織開発の進め方と、成功を導く鍵について触れてきました。


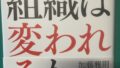
コメント